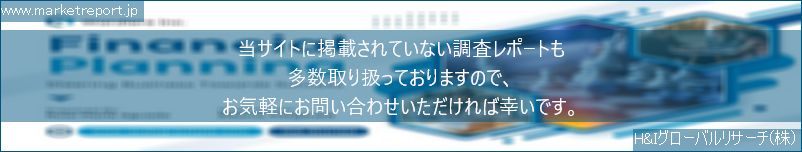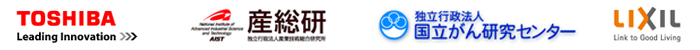1. 酸化銅
1.1. 一般情報、類義語
1.2. 組成、化学構造
1.3. 安全性情報
1.4. 危険有害性の特定
1.5. 取り扱いと保管
1.6. 毒性学的および生態学的情報
1.7. 輸送情報
2. 酸化銅の用途
2.1. 酸化銅の応用分野、川下製品
3. 酸化銅の製造法
4. 酸化銅の特許
概要
概要
発明の概要
発明の詳細な説明
5. 世界の酸化銅市場
5.1. 一般的な酸化銅市場の状況、動向
5.2. 酸化銅のメーカー
– ヨーロッパ
– アジア
– 北米
– その他の地域
5.3. 酸化銅のサプライヤー(輸入業者、現地販売業者)
– 欧州
– アジア
– 北米
– その他の地域
5.4. 酸化銅市場予測
6. 酸化銅市場価格
6.1. 欧州の酸化銅価格
6.2. アジアの酸化銅価格
6.3. 北米の酸化銅価格
6.4. その他の地域の酸化銅価格
7. 酸化銅の最終用途分野
7.1. 酸化銅の用途別市場
7.2. 酸化銅の川下市場の動向と展望
酸化銅は黒色の粉末状の固体で、金属銅が酸素と反応することにより生成します。この物質は、pHが6以上の環境で安定であり、酸性条件下では溶解する性質を持っています。密度は約6.3 g/cm³で、融点は1,200°Cに達します。鉱物としての酸化銅は、テノライト(tenorite)としても知られており、自然界では稀に見られるものの、人工的に製造されるのが一般的です。
酸化銅の特性は、多くの産業用途で重要な役割を果たしています。その一つは、優れた導電性と半導体的性質です。このため、酸化銅は電子材料や太陽電池、触媒として広く利用されています。特に、p型半導体としての性質を持つため、電気伝導性を有する物質との接合により多様なエレクトロニクスデバイスの性能を向上させる効果があります。
また、酸化銅は抗菌性を有しており、バクテリアや菌類の成長を抑制する働きを持つため、農薬や防腐剤、抗菌剤として利用されることもあります。さらに、鮮やかな青色を呈する他の銅化合物と異なり、酸化銅は黒色のため、顔料としての用途もあります。特に、ガラスや陶器の釉薬として使用され、美しい色合いを生み出すことができます。
酸化銅は、さまざまな方法で製造されますが、代表的なのは銅の腐食による湿式法と、酸素中での直接酸化による乾式法です。湿式法は、銅を硝酸で溶解し、得られた銅溶液を加熱することにより酸化銅を析出させます。一方、乾式法では、高温条件下で金属銅を直接酸化することにより、酸化銅を得る方法です。これらの方法により製造された酸化銅は、その純度や結晶構造を調整することが可能であり、用途に応じた製品を提供できます。
酸化銅に関連する特許は多数あり、その多くは電子材料、触媒としての用途に関するものです。例えば、酸化銅を用いた効率的な太陽電池の製造方法や、新しい形の半導体素子の開発、さらには抗菌作用を利用した医療用素材の改善に関する技術などが挙げられます。酸化銅のナノ粒子化技術も、近年注目されている分野の一つです。ナノ尺度での酸化銅は比表面積が大きく、反応性が高いため、先進的な材料設計において重要な役割を担っています。
このように、酸化銅は多岐にわたる分野で活用されており、その特性を生かした新たな応用が期待されています。特に、再生可能エネルギー分野や環境技術において、その応用研究は今後も進展することでしょう。氧化銅は、基礎から先端技術に至るまで、私たちの生活を豊かにするために欠かせない化学物質として、その重要性がますます増しています。