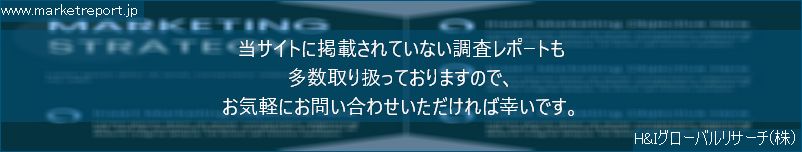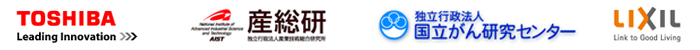1. デュラファンギン
1.1. 一般情報、類義語
1.2. 組成、化学構造
1.3. 安全性情報
1.4. 危険有害性の特定
1.5. 取り扱いと保管
1.6. 毒性学的および生態学的情報
1.7. 輸送情報
2. デュラファンギンの用途
2.1. デュラファンギンの応用分野、川下製品
3. デュラファンギンの製造法
4. デュラファンギンの特許
概要
概要
発明の概要
発明の詳細な説明
5. 世界のデュラファンギン市場
5.1. 一般的なデュラファンギン市場の状況、動向
5.2. デュラファンギンのメーカー
– ヨーロッパ
– アジア
– 北米
– その他の地域
5.3. デュラファンギンのサプライヤー(輸入業者、現地販売業者)
– 欧州
– アジア
– 北米
– その他の地域
5.4. デュラファンギン市場予測
6. デュラファンギン市場価格
6.1. 欧州のデュラファンギン価格
6.2. アジアのデュラファンギン価格
6.3. 北米のデュラファンギン価格
6.4. その他の地域のデュラファンギン価格
7. デュラファンギンの最終用途分野
7.1. デュラファンギンの用途別市場
7.2. デュラファンギンの川下市場の動向と展望
アニドゥラファンギンの化学特性について述べると、この物質は複雑な環状ヘプタペプチド構造を持ち、リポペプチドとしての性質を示します。化学式はC58H73N7O17であり、その分子量は1140.25 g/molです。このような大きな分子サイズは、低い経口生物利用能を示すため点滴として投与されます。また、アニドゥラファンギンは水に対しては低い溶解性を持ち、投与が困難であるため、臨床では通常溶媒に溶解してから使用されます。
アニドゥラファンギンの主な用途は、侵襲性カンジダ症の治療です。特に、カンジダ血症や食道カンジダ症などの重篤な感染症に対して効果を発揮します。その作用機序は、真菌の細胞壁の重要な構成要素であるβ(1,3)-D-グルカンの合成を阻害することにより、真菌の増殖を抑制することです。このようにして、真菌の細胞壁を脆弱にし、結果としてオスモティックショックにより真菌を死滅させます。他の抗真菌薬に比べ、アニドゥラファンギンは肝毒性が少なく、相互作用のリスクも低いことから、特に免疫不全患者の治療において優れた選択肢とされています。
アニドゥラファンギンの製造方法については、微生物発酵法と化学合成が組み合わされたプロセスが一般的です。具体的には、特定のfungal strainsが発酵によりアニドゥラファンギンの骨格を生産し、その後の化学修飾を施して完成形の薬用成分が得られます。製造工程は厳密な品質管理が求められ、特に純度の高い製品が要求されます。製剤化には、安定性の確保と適切な溶解度を達成するための技術が活用されています。
アニドゥラファンギンに関連する特許は、化学構造そのものに対する特許、製造法に関する特許、医療用途に関する特許などが存在します。これらの特許は主に製薬会社が出願しており、新たな治療法の開発や製造プロセスの効率化に寄与しています。特許は、アニドゥラファンギンの商業的利用を保護し、市場における競争優位性を維持するために重要です。
以上がアニドゥラファンギンに関する一般的な情報です。この薬剤は、その特異な作用機序と安全性により、真菌感染症の治療において貴重な役割を果たしています。研究開発や技術革新により、このような抗真菌薬の利用可能性がさらに広がることが期待されています。