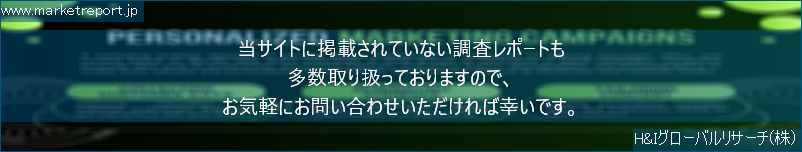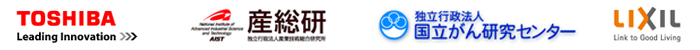1. グルタミン酸ナトリウム
1.1. 一般情報、類義語
1.2. 組成、化学構造
1.3. 安全性情報
1.4. 危険有害性の特定
1.5. 取り扱いと保管
1.6. 毒性学的および生態学的情報
1.7. 輸送情報
2. グルタミン酸ナトリウムの用途
2.1. グルタミン酸ナトリウムの応用分野、川下製品
3. グルタミン酸ナトリウムの製造法
4. グルタミン酸ナトリウムの特許
概要
概要
発明の概要
発明の詳細な説明
5. 世界のグルタミン酸ナトリウム市場
5.1. 一般的なグルタミン酸ナトリウム市場の状況、動向
5.2. グルタミン酸ナトリウムのメーカー
– ヨーロッパ
– アジア
– 北米
– その他の地域
5.3. グルタミン酸ナトリウムのサプライヤー(輸入業者、現地販売業者)
– 欧州
– アジア
– 北米
– その他の地域
5.4. グルタミン酸ナトリウム市場予測
6. グルタミン酸ナトリウム市場価格
6.1. 欧州のグルタミン酸ナトリウム価格
6.2. アジアのグルタミン酸ナトリウム価格
6.3. 北米のグルタミン酸ナトリウム価格
6.4. その他の地域のグルタミン酸ナトリウム価格
7. グルタミン酸ナトリウムの最終用途分野
7.1. グルタミン酸ナトリウムの用途別市場
7.2. グルタミン酸ナトリウムの川下市場の動向と展望
MSGの特性としては、水に非常に溶けやすく、無臭で、強い旨味を持つ白色の結晶性粉末です。物理的には比重1.62で、融点は232°Cです。溶解するとナトリウムイオンとグルタミン酸イオンに解離し、これが旨味を感じさせる要因となります。MSGの安全性については、一般に「安全である」とされていますが、大量摂取による健康への影響については議論があります。たとえば、一部の人々は「中華料理症候群」と呼ばれるMSGによる一時的な症状を訴えますが、科学的な証拠に基づいた決定的な関連性は示されていません。
MSGの主な用途は食品産業における調味料としての利用です。スープ、ソース、加工食品、スナック菓子などで風味を強調するために使用されます。また、家庭料理でも味を引き立てるために添加されることがあります。MSGは食品の塩味、甘味、酸味、苦味のどれにも属さない「第五の味」である旨味を担っており、日本料理においては特に重要な役割を果たします。さらに、MSGは低ナトリウム食品の開発にも役立ち、塩分の摂取量を減らしつつ味を損なわない食品の製造に貢献しています。
MSGの製造方法に関しては、主に発酵法が採用されます。発酵法では、砂糖ビートやさとうきびから得られる糖蜜をもとに、Corynebacterium属の細菌を使ってグルタミン酸を発酵させます。この過程で得られたグルタミン酸を精製し、ナトリウムと反応させてMSGが生成されます。発酵法は生産性が高く、比較的低コストで環境に優しい方法として広く普及しています。
MSGに関連する特許情報は、製造技術やその応用に関するものが多く存在しています。たとえば、特定の細菌株の使用や発酵プロセスの改良、新しい用途の開発などが特許として申請されています。顕著なものとしては、より効率的に高純度のMSGを生産するための技術や、特定の食品に最適化したMSGの利用方法が挙げられます。
このように、モノナトリウムグルタミン酸は日常生活の中に深く浸透しており、さまざまな形で私たちの食経験を豊かにしています。科学的研究が進むにつれてその応用範囲も広がり、新たな調理技術や食品科学の発展に寄与する可能性が期待されています。MSGの安全性については、科学的なレビューが続けられ、信頼できるデータに基づいた理解が求められますが、適切に使用される限り、日常の食事において有益な調味料であることは間違いありません。