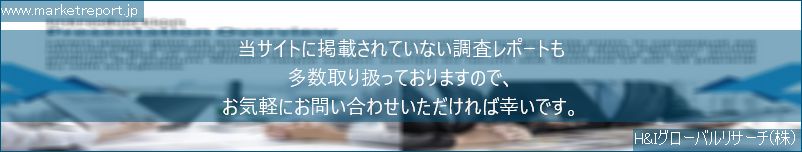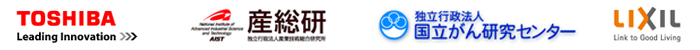1. ベンズブロマロン
1.1. 一般情報、類義語
1.2. 組成、化学構造
1.3. 安全性情報
1.4. 危険有害性の特定
1.5. 取り扱いと保管
1.6. 毒性学的および生態学的情報
1.7. 輸送情報
2. ベンズブロマロンの用途
2.1. ベンズブロマロンの応用分野、川下製品
3. ベンズブロマロンの製造法
4. ベンズブロマロンの特許
概要
概要
発明の概要
発明の詳細な説明
5. 世界のベンズブロマロン市場
5.1. 一般的なベンズブロマロン市場の状況、動向
5.2. ベンズブロマロンのメーカー
– ヨーロッパ
– アジア
– 北米
– その他の地域
5.3. ベンズブロマロンのサプライヤー(輸入業者、現地販売業者)
– 欧州
– アジア
– 北米
– その他の地域
5.4. ベンズブロマロン市場予測
6. ベンズブロマロン市場価格
6.1. 欧州のベンズブロマロン価格
6.2. アジアのベンズブロマロン価格
6.3. 北米のベンズブロマロン価格
6.4. その他の地域のベンズブロマロン価格
7. ベンズブロマロンの最終用途分野
7.1. ベンズブロマロンの用途別市場
7.2. ベンズブロマロンの川下市場の動向と展望
ベンズブロマロンの化学式はC17H12BrNO3であり、その分子構造にはブロモフェニル基とアミノ酸の一種であるピリドン環が含まれています。この分子構造により、腎臓の尿細管における尿酸の再吸収を抑え、尿中への排泄を促進します。特に、腎機能が低下している患者にも効果が認められる点で、他の尿酸降下薬に比べて有益な面があります。
物理的特性としては、ベンズブロマロンは白色の結晶性粉末で、メチレンジクロライド、ジエチルエーテル、そしてエタノールなどの有機溶媒に可溶です。また、室温における安定性が高いことから、製剤化にも適しています。
臨床用途として、ベンズブロマロンは慢性の高尿酸血症の治療において重要な役割を果たします。これにより、痛風発作の予防や尿路結石の形成を防ぎ、患者の生活の質を向上させることが期待されます。特に、アロプリノールなどのキサンチンオキシダーゼ阻害薬に耐性を示す患者に対して、有効な代替治療法となることがあります。
しかし、ベンズブロマロンの使用にはいくつかの注意点があります。肝機能障害を引き起こす可能性があり、このために一部の国では市場から撤退したこともあります。使用を開始する前に肝機能を慎重に評価し、治療中も定期的なモニタリングが推奨されています。
ベンズブロマロンの製造方法としては、ブロモフェニル基化合物とピリドン誘導体を反応させることが一般的な手法として知られています。この反応は通常、適切な溶媒と触媒の下で行われ、得られた生成物は精製工程を経て医薬品として使用可能な品質に仕上げられます。
関連する特許としては、合成方法の改良や新たな製剤形態に関するものが多数存在します。例えば、製造コストの削減を目的とした新技術や、副作用を低減するための徐放性製剤などが特許として出願され、技術面での進化が続けられています。
以上のように、ベンズブロマロンはその優れた薬理作用により、痛風や高尿酸血症の治療において非常に貴重な選択肢となっていますが、使用に際しては適切な医療監視が求められます。これにより、安全かつ効果的な治療を提供し、患者のQOL向上に寄与することが可能です。日本を含むいくつかの地域では依然として医療現場で活用されていますが、グローバルな視点で見ると、その使用は上記の懸念から限定的となっている場合もあります。それゆえ、ベンズブロマロンの利用に関する最新の研究や臨床指針を常に参照し、最善の治療方針を選択することが重要です。